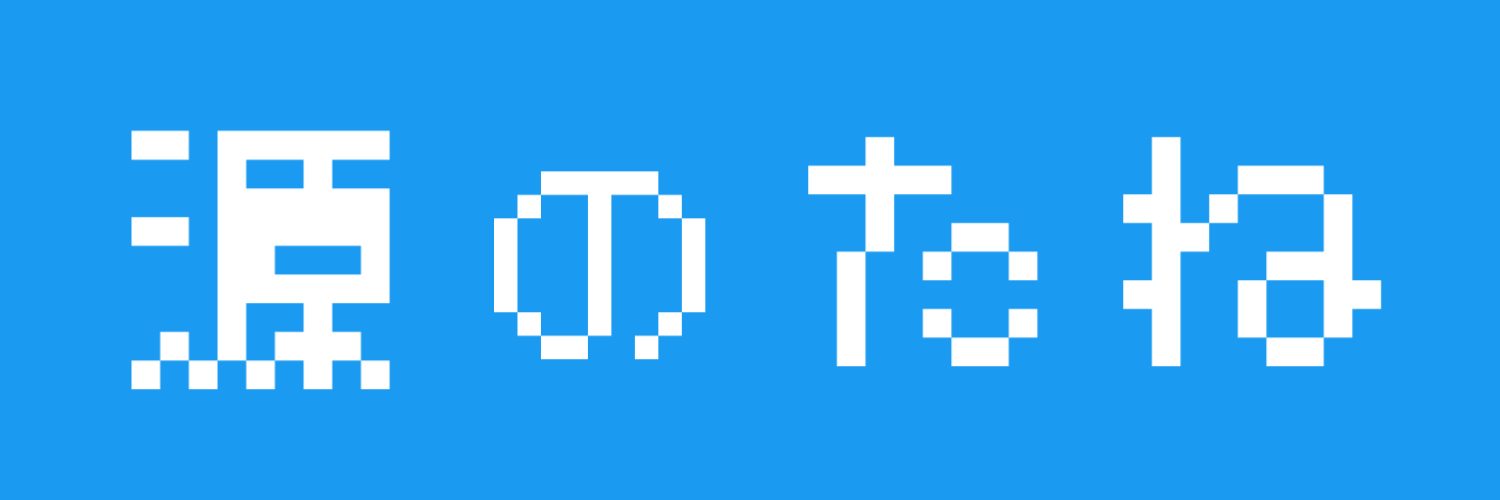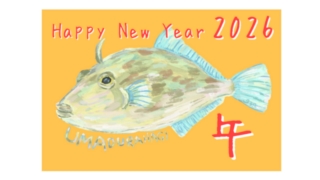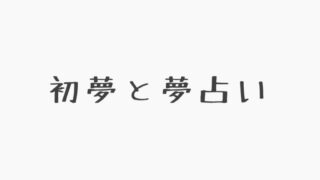正月とおばあちゃんと箱根駅伝
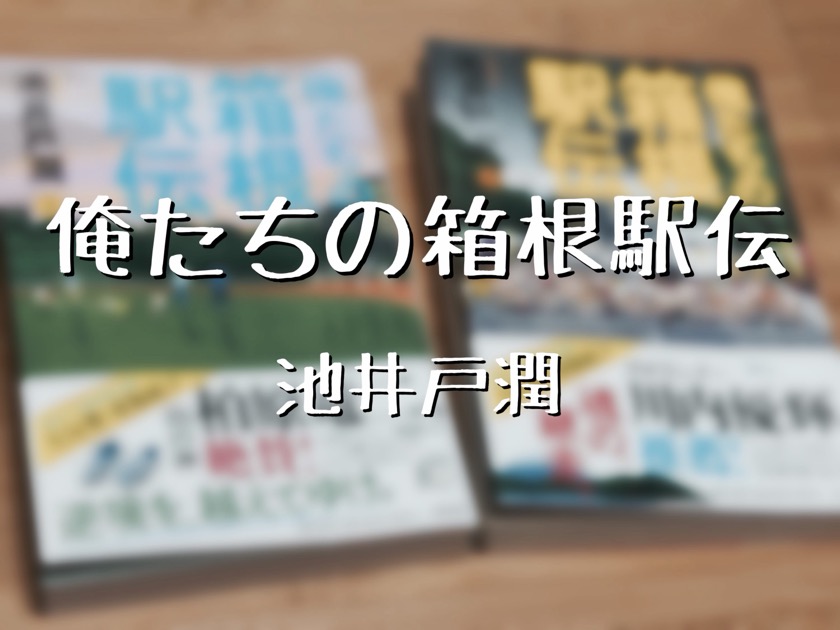
毎年、年末年始は祖父母の家で過ごすのが、うちの家族の恒例だった。
年末は歌番組をみんなで観て、年始はお雑煮を食べながら、いかにも「正月」という時間を過ごす。
ただひとつだけ、昔から不思議なルールがあった。
それは、1月2日と3日は祖父母の家になるべく行かないようにしよう、というもの。
小さい頃の僕には、その理由が分からなかった。
あんなに楽しく過ごしていたのに、どうしてその2日間だけダメなんだろう、と。
あとになって分かったその理由は「箱根駅伝があるから」だった。
祖母は昔から箱根駅伝の大ファンで、毎年2日と3日はテレビ中継をつけ、メモを取りながら真剣な表情で観ていた。
中継に集中している祖母の時間を邪魔しないように、祖父母の家に行かないようにするというのが2日間行かない理由だった。
だから今の僕の中では「箱根駅伝」といえば、自然と「正月のおばあちゃん」と結びついている。
正直、子どもの頃の僕には、なぜそこまでして人が苦しそうに走っている姿を観て楽しめるのか分からなかった。
ただ、「箱根駅伝には、きっと何かあるんだろうな」という漠然とした印象だけが、心のどこかに残っていた。
池井戸潤さんの『俺たちの箱根駅伝』を読んだ。
冒頭に書いた、子どもの頃に感じていた
“箱根駅伝には何かある”
という感覚を、この本を読みながらふと思い出した。
今だから言えるけれど、小さい頃の自分はかなり偏った見方をしていたと思う。
箱根駅伝って、淡々と走る地味な競技、という印象があったし、
“ 箱根駅伝のせいで ”お正月に祖母の家から追い出されているような、そんな苦手意識もどこかにあったのかも知れない。
でも、この本を読んで、その印象は完全に覆された。
「え、こんなに熱くて、こんなに深いスポーツだったのか」
読み進めながら、気がつくと呼吸をするのを忘れて読み進め、何度も目頭が熱くなり目が潤んでいた。
周囲から煙たがられ、冷ややかな言葉を浴びながら、それでも走る学生連合チームと甲斐監督。
最初はバラバラで、モチベーションも上がらないチームだったのに、“人の想い”が少しずつ噛み合っていく。
想いって、こんなにも人を動かす原動力になるんだな、と胸を打たれた。
それぞれがいろんなものを背負って走り、言葉ではなく、走りそのもので意思を示そうとする姿が、ただただかっこいい。
箱根駅伝について詳しくなかった僕でも情景が浮かぶほど、描写はとても丁寧で、この物語は箱根駅伝を通して、人の意思、熱くて純粋なエネルギーが人を動かす、ということを描いているように感じた。
それは、社会で生きている僕たちにも、そのまま重なる話だと思う。
そして、この作品でもうひとつ印象に残ったのが、箱根駅伝の番組を作る側の人たちの描写だった。
現場のことを分かっていないのに、権力だけを持って口出しし、環境を悪くしていく人。
一方で、「いい番組」を作るために、立場を越えて関わり、想いを受け継いでいく人たち。
視聴率という数字だけを追うのではなく、箱根駅伝という文化や伝統、タスキをつなぐ人、その裏で支える人たちまで丁寧に伝えようとする姿勢が、とても印象的だった。
順位が入れ替わり、シーンが切り替わる、その一瞬の合間に選手の背景を差し込む。
ああ、これはプロの仕事だな、と素直に感心した。
一度は予選に敗れ、箱根駅伝への出場を断念せざるを得なかった“敗者”だからこそ持てる視点。
ただタスキをつなぐための走りではなく、
自分たちの存在意義を証明するための走り。
この物語を読み終えた今、
子どもの頃、正月に真剣に箱根駅伝を応援していた祖母の姿が、少し違って見える気がした。
今日、明日は箱根駅伝。
いつか箱根で感じてみたい。
2026年には日テレでドラマ化もするみたいだし楽しみ。